トップページ ≫ 文芸広場 ≫ 県政の深海魚(7)「汚れた市長選‐大量の逮捕者・前編」
文芸広場
俳句・詩・小説・エッセイ等あなたの想いや作品をお寄せください。
春彦のテーマは〝変わること〟となった。
市議会議員の選挙でも大きく他を離してトップ当選だったが、安穏としていてはいけないと思った。
「信濃君、決断してくれ。市長に出るんだ。今のH市ではだめになるばかりだ。市長の西川も、もう四期だ。信濃君しかいない。信濃君しかこの街は変えられないよ」
医師の広瀬がいつになく真剣に訴えた。
正義感の強い広瀬は、H市の青年達からも尊敬されていた。彼は外科医として毎日が決断の日々だった。手術か否か。他に対しても早い決断を迫った。
「脱皮せざる蛇は亡びる― ニーチェも言ってるじゃないか」
広瀬はよく本を読んでいた。
「この街を変えて行こう。俺たちはふる里のまちに責任と使命を持って生きていかなければ駄目だ」
広瀬は自分の言葉に酔っていた。
青年の〝気〟が広瀬の体全体から醸し出されていた。
「やりましょう」
この一瞬の決断が春彦を変えた。
「男子、この世に生を受けたるは事を成すにありですね」
春彦は坂本龍馬のこの言葉を好んでいた。
広瀬の手が春彦の手を握りしめた。強い血流と血流が交じり合ったようだった。
広瀬と春彦はこの握手を期に〝街づくり〟の鬼と化した。
二人はH市の路地という路地を無言で歩き続けた。
月光が二人の影を大きなものに創り上げた。
その夜、月は満ちていた。
「チャンスとはこういうものだな」
春彦はその夜、夢をみた。
大海原に出た小舟に怒とうのような波が襲いかかった。その度に春彦の乗った舟は巨大な舟になっていた。振り返ると、何百艙もの舟が春彦の舟の後についてきた。
「奴が、いよいよ出るようですぜ」
山崎が怒ったように杯を卓においた。
「やっぱりそうか」
市長の西川はいつになく不安そうな面持ちで呟いた。
「奴はね、若い連中におだてられてしまったみたいだね。三十代で市長なんて、この街を舐めてるってことよ」
老獪な小田が吐き捨てるように言った。
「あっしはね。せいぜい、あと二期はやりてえんでさぁ。それで六期、何とか頼みまさぁ」
こんな時の西川はまるで子供だった。
選挙の戦略なんて分かる筈もなく、山崎や小田に全部任せて今日までやって来たのだ。
選挙といえば金。
金をどれだけ使ったらいいのか。それだけで彼は精一杯だった。
「まあね、市長。俺達に任せてくれ。なあ、山崎さん」
尋ねられた山崎は黙って庭先の青々とした竹を見つめていた。その竹の節を目で追いながら言った。
「そうよな。ざっと一億だろうな」
「安いもんだ。市長の山の木を二百本切ればいいってことだな」
小田は薄笑いを浮かべながら、市長の西川の顔を窺った。
間髪を入れずに山崎が唱えた。
「ええと・・・各地区のボス達に五十万ずつ、それで五千万。議員の奴等にはランクをつけて三千万、あとは徹底した飲み食いをさせて二千万というところでさあな」
勿論、それは上辺の話で、山崎と小田の分が二千万近く計算に入れられていた。
「ところで、議員には気をつけなけりゃならんな。いくら若造の信濃だって心情的に奴につながっている議員もいるかもしらんしな」
こういうところがいかにも山崎らしかった。油断は禁物だということを百戦錬磨の経験から彼は知りつくしていた。
「誰だい?信用できるのは。なあ、小田さんよぉ」
山崎は三白眼の目で覗き込むように聞いた。老獪と狡猾で固めた山崎の五体が青い炎となって、暗い光彩を放った。山崎が汚れきった夢に燃え滾る瞬間だった。
「ああ、あのな。まず北上、木曽、宮崎、芦田、吉井・・・ウーン・・・まずこの五人は大丈夫だな」
小田が名前を挙げた五人は紛れもなく小田の弟分だった。そして西川の信奉者だった。
「あと五、六人はまあ、俺にまかしといてくれ」
小田が名前をあえて濁したのは訳があった。中間色にぼかしておいて一千万近くの金を自由にしようという魂胆からだった。市長の西川はひたすら沈黙を守った。
「そうだな、あと議員のOBだな。十人ぐれえになるな」
小田の銅臭にまみれた顔がゆるんだ。
「また、ここから抜くことができるな・・・」小田は心の中で呟いた。
「ようし、前祝いといくか、酒だ」
千代菊が狐のように入ってきた。戦いはこの狐の最も好物のエサだ。
神のような予知能力がこの女狐の五感を振るわせた。
「撒き屋」という男達がいる。男達といっても四、五人という少人数だ。
選挙が近づくと「撒き屋」達の血がうずく。彼らは「撒く」ということに一身を賭していた。
この男達の利益率は三割。彼らが地域のボス的存在に近づいていく。
ボス達は「待ってました」とばかりに金を受け取る。
勿論、撒き屋達はそのボス達の力量をしっかりと斟酌している。人によっては三十万、五十万と差をつけた。
「じゃあ、まあ、宜しくな」
撒き屋の決まったセリフだった。
ボス達は貰った金の一割から二割を懐に入れる。残りの八割は義理堅く知り合いに配った。
まず、世間話をする。そして、選挙。
「やっぱり西川しかいねえよな」「じゃあまた」
帰り際に必ず封筒を置いてくる。一万から二万の現金が封筒の中にじっと潜んでいた。
七人の市議会議員が小田の家に集った。
「今度の市長選の費用だ。何も言わずにしまってくれ。これはと思う奴等には飲ませてくれ。勿論、金が必要だと思ったら渡してくれ。足りなくなったら俺に言ってくれ。充分、資金は用意してあるかんな」
暗い表情で小田が言った。
「じゃあ」一人ずつに茶封筒が配られた。茶封筒がはちきれそうだった。その厚さが渡す方にも貰う方にも満足感を与えた。
「ありがてえな」
古参の北上がニヤニヤ笑いながら背広の内ポケットに分厚い封筒を押し込めた。
七人が帰った後、小田はある種の安堵感に浸った。
(奴等は間違いなく西川をやるな。金だけが信頼の鎖だ。)
小田の哲学は全て金。心を信じた途端、人間は不幸になる。
信念のように小田は思っていた。選挙も女も信じられるものは金―― 小田の歩んできた人生行路はみんなそんなものだった。
街が真っ二つに割れた。選挙は激戦を極めた。当初、西川陣営には油断があった。中盤戦から信濃春彦が優位にたった。
春彦は一日に三十回以上街頭に立った。辻説法を重ねた。夕刻の街頭演説には溢れんばかりの市民がどこからともなく集まってきた。春彦は島崎藤村の詩を頭に浮かべた。
〝血につながるふる里
心につながるふる里
言葉につながるふる里〟
春彦は訴えた。
「古いH市を今こそ変えましょう!皆さん!皆さんと一緒に、明日のH市を今日創りましょう!」
「私は、この若い生命をH市のために捧げます。全ての私心も捨てて、身を粉にして皆様のふる里のために、皆様のお子さんために、お孫さんのために、胸をはって誇れる私達の街を創りましょう!」
春彦の真剣な訴えは聴く者の胸に勢いを持って浸み込んで行った。
西川は慌てた。
芥川賞作家で国民的英雄としてその名を欲しいままにしていた国会議員が飛んできた。
「この歴史ある街を何も分からない未熟な若者に任せては危険だ」
若さが売り物で何百万という未曽有の得票をした作家の奇妙な演説に春彦は失笑した。
三千人を超す聴衆は歓声をあげた。この作家の行くところ全てが黒だかりの山となった。
――負けるものか・・・冗談じゃない!死んでも、絶対負けるものか!
春彦は赤い炎となった。
投票日があと三日と迫った。
夜の十時。
疲れた春彦の自宅に電話が鳴った。
「いたずら電話か?」
呟きながら春彦はおもむろに受話器を取った。
「お疲れのところ、誠にすみません。私は西南総業の富士と申します。以前、先生とは名刺交換をさせて頂きました」
富士といえば西南総業のナンバーファイブ。らつ腕の不動産担当の役員だ。
「はあ?で、用件は何です?」
春彦は相手が相手だけに、あえて冷たい対応をした。
「実は明日、何時でもよろしいですから二、三十分頂けますか」
丁寧過ぎるくらいの猫なで声で富士は言った。
「とにかく、僕は選挙戦のデットヒートの中にいます。申し訳ないのですが、時間は無いですね」と春彦。
「いえいえ、先程、二、三十分と申しましたが、十分くらいお時間を頂けますでしょうか。どうしてもお耳に入れたいことがありまして・・・」
富士の声は哀願に変わっていた。
――何だろう・・・耳に入れたいこと・・・? 春彦は迷った。
「それでは午後三時、本当に十分にして下さいよ」
突き放したように春彦は言った。身も心もくたくただった。
〝当選〟 この二文字だけが今の春彦の人生だ。
睡魔が襲ってきた。地中の中に深く沈むように春彦は寝入った。
バックナンバー
新着ニュース
特別企画PR






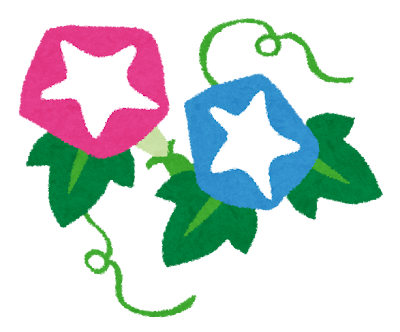



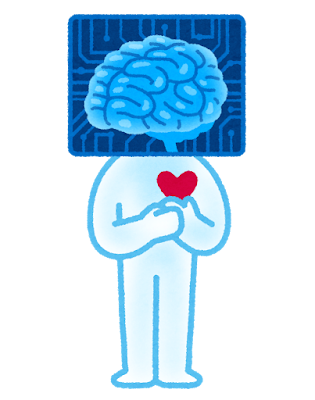
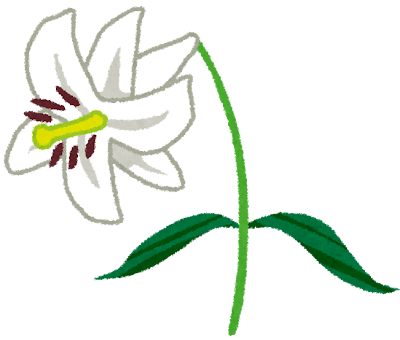




![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](http://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)

