トップページ ≫ 文芸広場 ≫ 県政の深海魚(26)「終章」
文芸広場
俳句・詩・小説・エッセイ等あなたの想いや作品をお寄せください。
花の時の短さ、権力の危うさ、欲望の虚しさを千曲も春彦も全く違う場で感じていた。
春彦は仏教の説く「無明」を噛みしめていた。
―― 自分の思い通りになる世界を引きずりながら生きようとすると無理がかかり苦しみが起こってくる。自分の存在をあまりにも絶対視すると「生きる悲しみ」の原因を倍化させる・・・。
何処かで読んだ仏教の書の一節が重たい現実味を帯びて春彦の脳裏といわず五体の全てに突き刺さってきた。
春彦は深い感慨を引きずりながら紀尾井坂を訪ねた。あの時から三年の歳月が流れている。
礼子の手紙から数日が過ぎていたが、逢うのは確か一年ぶりだ。
―― この一年で礼子の容色は衰えていないだろうか。女はある年を過ぎると急激に色香が失せる場合がある・・・。
春彦は余計な事に気がついて苦笑いをした。礼子に申し訳ないとも思った。
茶房「紀尾井」は三年前と同じように青春がたちのぼっていた。静寂の中に品格のある活気があった。
春彦は窓側の小さなシャレた椅子と柔らかな丸みを帯びたテーブルの席を選んだ。
礼子を待った。
数分もたたないうちに礼子がやって来た。
あの独特の微笑みを身体全体に纏いながら。
美貌は少しも失せていなかった。
「待ちました?本当、久しぶりです」
「そうだったね。ごめん、ごめん。本当色々あって・・・」
当たり前のような言葉が交差した。
「お手紙では春彦さんの現状は知っているのだけれどその後、本当、心配していたわ」
「うん、充電というところかな」
「動きのない春彦さんなんて想像できないわ。でも、相当疲れてしまったんじゃない?痛々しいわ。大変だったわね・・・」
「色々礼子さんには迷惑を掛けてしまってすまなかったね。何か、あなたの人生まで巻き込んでしまったようで胸が痛むよ」
「全然。春彦さんに出会ってなかったら今の自分はありえないわ。私・・・本当に、こんなにも人間って出会いによって変われるものかとびっくりしているの。感謝だわ、春彦さんに」
二人の会話はとめどなく続いていった。
春彦は急に態度を改めた。礼子の眩しさに負けまいと必死になった。そして百年はゆうに超えたであろう紀尾井坂の歴史を秘めた緑樹に目線を移した。しばらくして顔を礼子に向け直した。
礼子は春彦を見つめながら、春彦が今までとは違った何かの道に向かっていくなと直感した。
「僕はね、もう何と言うのかな・・・。賭けるということに幕を下ろしたいんだ。だからという訳ではないけど、これからは僕自身が、全く別の立場から高い志を抱いて社会を切り拓いていこうとする者達の支えになりたいんだ。この数年、複数の政党から国政への依頼を強く要請されたんだ。でもね、僕はありがたかったけど、心が全然炎となっていかない僕自身を発見して、断念しちゃったんだ。僕が敗れても僕の持ち続けてきた理想は決して敗れてはいない筈なんだ。そして、激しい戦いの歳月を生きてきて、恥ずかしいけど、ふっと気がついたことがあるんだよ。ハッとしたと言うのかな。僕はね、僕自身の中にあるもう一人の自分、そうだね、僕の影と言ったらいいのかな。そんな影を痛いほど見ちゃった・・・うん、まあ、知っちゃったというのかな・・・」
「影?」
「そう。その人間の影こそ生きとし生きる人間の実態かもしれないね。その影がどうも僕の歩みとは逆に行こう、逆に行こうと引っ張るんだよ。本当の姿っていうのは、もっと本当の僕らしさを生かした社会や人のために尽くす生き方があるだろと言っているんだよ。長い間、僕はその影の言葉にじっと耳を傾けたことがなかった気がするんだよ。今日まで僕はかなりの喪失感のようなものを味わってきたなぁ。でもね、その喪失の痛みっていうのかな。そのことに耐えてはじめてさ、今まで以上に大きな世界に出会えるんじゃないかなという思いに達したんだ。だから僕にとって喪失なんていうものがもたらす哀切感なんてものは峠から谷に降り立っていく霧にすぎないんだな。そんなような思いもよらない精神の革命ができたような気がしてならないんだ。ちょっとオーバーな表現だけどさ。死と同じように絶対避けられないのは生きることだよね。確かチャップリンが言っていた気がするな・・・」
かなり自分に酔いしれていることに気づきながらも春彦は続けた。
「まず一隅を照らしたい。その光を段々広げていく事が僕の使命じゃないかなと思っているんだ。初々しい青年政治家を育てていくためにあらゆるエネルギーを放出させたいんだ。その礎というかなあ、まあ捨石になりたい、そんなとこなんだよ」
礼子は目の前の春彦を、今までとは全く違った、まるで別人のような一人の男としてに見つめ直した。そして己より、他者のために身体を張って生きていこうとする春彦に改めて〝人間、信濃春彦〟を感じていた。と同時に瞬間、全く別の想いにかられた。
(この人って、いつも激しく挑戦していきながら、例え勝っても美酒に酔えず、敗れても、たたかれても、淡々として生きていられる・・・。この人の人生に賭けていく情熱って、いつも砂漠のように乾ききったところで燃え立たせ、もうこれ以上伸びきらない炎のように滾らせつづける・・・なんとも不思議な情熱の所有者。表現しがたいチャレンジャーっていう人なんだわ。きっと・・・。)
「春彦さん、ちょっといい?私ね、千曲の公判も全て取材してきたの。千曲は少しもたじろがない。尋問する検事を睨み、例え間違っていても自分の正義は曲げなかった。凄い男を感じたわ。でもね、清々しさとか清冽さは微塵も感じなかったし政治家の風格も覇者としての貫禄も全然なかったわ。勿論人間の矜持もね。自分を変えようとしていないのよ。自己変革のかけらも見られなかったわ。春彦さんとの大きな違いはそんなところにあるとつくづく思ったわ。唯一つ言えることがあるわ。これは全く女の勘だけど・・・。千曲は公判の時も服役中にもいつも頭の片隅に春彦さんがいたと思うの。皮肉にも囚われの身となって一番懐かしく思えたのは春彦さんであり、春彦さんとの日々だと私はすごく感じちゃったの。公判中の身でありながらも、再び県議に帰り咲いて、有罪となってまた失職して。私ね、千曲もね、春彦さんとは全く違うけど出直してくると思うわ。ある仮面をつけてね。そして千曲は再び野望と欲望という不逞な光を秘めながら自分の全人生を賭けて権力の坂をのぼってくると思うの。あの人こそ、良くも悪くも賭けることを知ってる人だわ」
まくし立てるように礼子は一気に喋り続けた。
陽が長い真夏の外はかなり暗くなっていた。
茶房「紀尾井」はそんな頃からシャレたバーに変わる。薄暗い海底のようなバー「紀尾井」となる。
人はそれぞれが海底の中の生物のようになって動かない。薄明かりはあたかも深海魚の発光のように光彩がなかった。
「私ね、つくづく県政って海底みたいなところって思ったわ。人々の目が行き届きにくい、人々の光も眼も決して届かない海の底。太陽光の届かない深海には光合成を行う海藻や植物プランクトンが存在しないから、そこに息づく深海魚達は浅海で消費されなかった生物の遺骸や排泄物がマリンスノーとなって沈降し深海に降り積もる。これらはある種の深海生物によって消費されるけど結局は大型の深海魚によって食べられていく。彼らは恐ろしいほどの水圧に耐えながら、生命を保たなければならないからその骨格は想像を絶する程頑丈なものになって、時には浅海の魚等を脅し、喰いちぎり、自らを肥やしていく。しかし、この生態はなかなかつかめない・・・。一見、表面は静けさを保っているけど海底は常に不穏。やっぱり春彦さんは別の魚族だわ。あっ、それと私ね、ここで新聞社を正式に辞めるって決めたの。もう深海魚なんて見なくていい。さっぱりしたわ。春彦さんの次の仕事、新しい挑戦、何でも手伝うわね。いえ、改めて・・・手伝わせて下さい」
礼子はそう言って微笑んで頭を下げた。
海底のようなバーは次第に更けていった。
魚影が一つ、一つ消えていく・・・。
その魚影にふと千曲の姿を見た気がした。
勿論、錯覚だ。しかし、礼子だけは錯覚とは思わなかった。刑期を終えた千曲は必ず春彦の前にもう一度、姿を現すとの確信のようなものを持っていた。再び深い海底に戻る前に・・・。
H市に帰った春彦に千曲からの電話が入ったのは紀尾井坂から五日程たった暑い日だった。
「信濃先生、暫くでした。千曲です。私は先生の言うとおりに生きていれば、こんな地獄を味わうことはなかったのです。信濃先生、これからは信濃先生の言うとおりに生きて参ります。どうかご指導下さい」
春彦は耳を疑った。
投獄、闘病、倒産の何れかを体験したものほど強いものはいない筈だ。
―― また骨格がさらに頑丈になって新しい泳法で深海に潜るのかな・・・。
S県の知事が変わった。
「新しい知事も海底に足を踏み入れなくてはならないよ」
何処か遠くの方から深海魚のささやき声が聞こえてきたように思えた。
「この俺もか・・・」
不服な形相で知事は呟いた。
(完)
バックナンバー
新着ニュース
アクセスランキング
特別企画PR






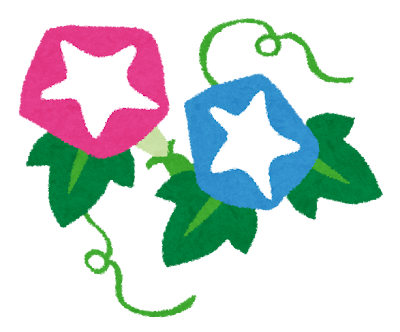



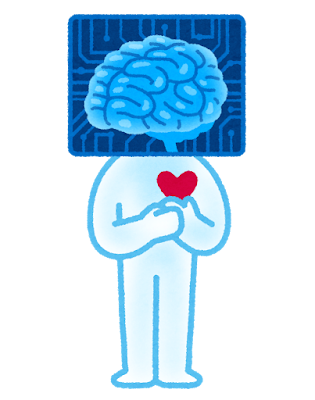
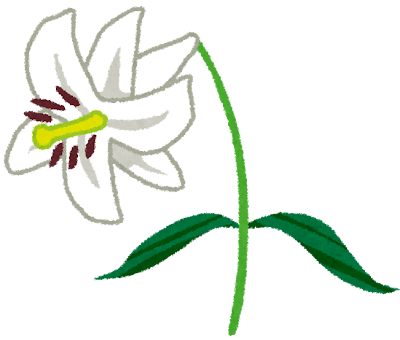




![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](http://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)

