文芸広場
俳句・詩・小説・エッセイ等あなたの想いや作品をお寄せください。
小川夏子はこの冬、六十半ばを迎えた。
何年か前まで、がむしゃらに仕事をしてきたので、そろそろ引退をし会社の経営を息子に譲った。
これからは誰に気兼ねすることなく、何に追われることなく、残りの人生を謳歌したいと思っていた。
そう思い、自問自答したところ、のんびりと旅に出たいと思った。ゆっくりと温泉に入りながら日本酒でも堪能しようかと。
その旅行先は特に決めていない。なぜなら急ぐ必要がないからだ。何十年も時間に追われていた夏子にとって、時間に縛られない日々はこの上ないものになるであろう。適当に足を運んだ駅を旅の出発駅にしようと心に決めた。
――ここは本当に駅なのかしら…。
そう夏子が思うのも無理はない。静寂に包まれたその駅には待合室もなく、無人駅のようだった。人の気配もない。空気の冷たさが一層、その駅をひっそりとさせた。
すぐのホームには、見知らぬ列車が停まっていた。
行き先は「夢行き」。
夏子は思わず目を疑った。
―― 果たして夢行きとは?子供の国みたいなものなの…?
するとその時、車掌なのか、一人の男が何処からともなく現れた。
夏子は男に「夢行きとは、どこの夢に行くのですか」と尋ねた。
男は真剣なまなざしでこう答えた。「僕の夢に行きます、どうぞご乗車ください」
夏子はさらに分からなくなった。この男が運転士なのか、車掌なのか、駅長なのか。夏子の迷いをよそに、この男は屈託のない笑顔を夏子に投げかけた。
―― まあ、急ぐ旅でもないから、外は寒いし、この列車に乗って、この方の夢とやらに行ってみましょうか。でも世の中は不思議な商売が多いものだわ…。
寒気と好奇心が夏子をその列車の車内へと導いた。
車内には何人かの乗客がいた。その顔も年齢も様々だった。夏子はあまり乗客に興味を示しては失礼になると思い、視線を窓の外に向けた。
と同時に大きな男の声がその列車に響く。
「夢行き?意味がわからないな、夢行きってどこに行くんだよ」とその大柄な男性は少し喧嘩腰に男に食ってかかった。夏子は年の功か少し微笑みながら、「まあまあ、とりあえず黙って乗ったらどうですか」と大柄な男性に話しかけた。
「まあ、あとでちゃんと説明してくれよ」そうぶつぶつ言いながら夏子の隣に座った。
出発しない列車のホームを眺めていると、今度はゆるキャラのような男が姿を現した。
「遅れてすみません」ふっくらふわふわした癒し系のゆるキャラのようだ。
そのゆるキャラが大きな声を張り上げた。「運転士の夢行きにご同行いただきましてありがとうございます。これにて出発します」
夏子はこの言葉から、僕と言った男が運転士で、このふっくらゆるキャラが車掌ということを把握できた。
夢行き列車がそのゆるキャラの甲高い声とともに動き出した。
すると隣にいた大きな男性が運転席にむかって叫んだ。「あんたが運転手だったんだな。いい笑顔じゃん。気に入った。あんたの夢までつきあってやるよ」と厳しい口調で声をあげていた。
―― 口調は激しいがこのひと、いいひとじゃない…。今どき、まっすぐなひとだわ…。
夏子の顔にはひそかに笑みがこぼれていた。
この列車はノンストップかと思いきや、各駅に停まった。
運転士は車掌とともにホームに立ち、頭を下げ、ホームにいるものに「乗ってください」と促した。
変わらぬ屈託のない笑顔を冬の柔らかな温もりのある日差しが二人をねぎらうかのように照らしていた。そのせいなのか二人の額からは汗がうっすらと浮かんでいた。
―― この運転士はとてつもない運を持ち合わせているわ、きっと彼はスターになる…。
ホームに立つ運転士を眺めながら、夏子の本能的な直感が夏子の頭を走り抜けた。
ホームからは何人かの乗客が乗り込んだ。その数は駅に停まるほどに増えていった。
そしてある駅に到着したとき、雨が降り出した。そして横なぐりの意地悪な雨が二人を襲った。
その雨は「どうぞ私の夢行きにご乗車ください」という運転士と車掌の声をかき消し、大きな音をあげていた。
その彼らをみた多くの乗客は列車に乗り込んだ。彼らの熱意に心を動かされたものが多かった。
運転士の夢を心から応援するもの、笑顔に惹かれたもの、いやそれだけではないようだ。雨宿りが目的なもの、ただ乗りできるというちゃっかりしたもの、貪欲なもの、なにかのもくろみがあるもの、さまざまなものがこの列車に乗り合わす。
出発から何時間、何日たったであろうか。
運転手がマイクを持った。
「もうすぐ私の夢に到着します。多くの方にご乗車いただき、夢につくもようです。ありがとうございました」
いつのまにか、このわずかな列車の旅、彼の夢が小川夏子にとっての夢となっていた。
夏子は長きに渡り仕事一筋だったため、誰かのために何かをすることを忘れていた。勿論、会社のため、社員のために日々生きていたことには違いない。しかし、仕事を離れ、誰かのために、ましてその人の夢に付き合うなど考えたこともなかった。
夏子はふと懐かしさを覚えた。そして記憶のなかに刻み込まれたセピア色の甘くほのかな初恋の思い出が心によみがえる。
その瞬間、
―― これは恋…?
夏子は何十年前からだろうか。事業を始めるちょっと前からこの恋というものを封印してきた。その頃から、そういう感情はもう心に芽生えることはないとずっと思ってきたのだ。
―― 恋を忘れていた私の最後の恋なのかしら…。
そう夏子は心の奥でひとり呟きながら、彼が夢に到着したときのことを想い描いていた。
多くの乗客が列車の終点に到着し、歓喜の声を挙げる。その歓声とともに、本当の涙を流すものは夏子同様、運転士に恋した乗客だろう、と少しクールな目で車内にいる乗客に目をやる。夏子は隣の大柄男性をちらっと横目に「きっとあなたも喜んで泣くかもね」と独り言をささやく。
夏子は、運転士の夢の実現と達成感からでた幸せな笑顔を見届けたらすぐに温泉に向かおうと心に決めた。
窓の外はさっきまで降っていた大粒の激しい雨が止んだようだ。
その列車の先は、彼の未来を予感させる七色の虹が色鮮やかに壮麗に浮かんでいた。
END
新着ニュース
- さくら草まつり2025(2025年03月22日)
- パールのピアスに憧れて(2025年03月17日)
- 泥酔は人生を変えてしまう(2025年03月31日)
- 二院制はどうなったのか(2025年01月10日)
アクセスランキング
特別企画PR









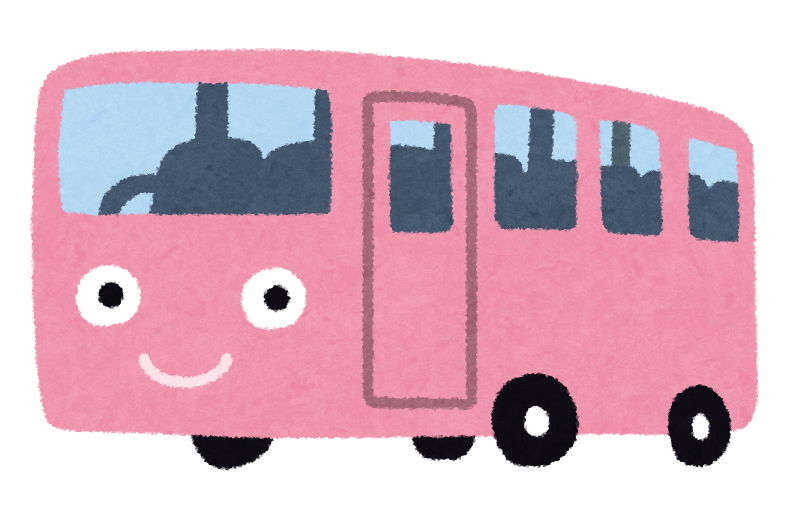

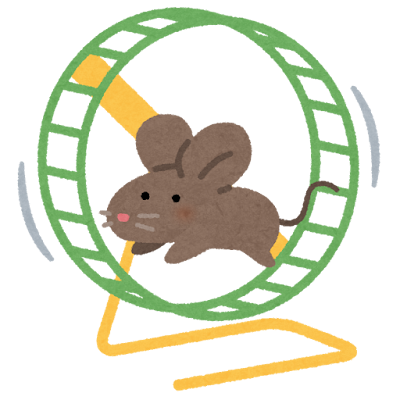






![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](http://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)

