トップページ ≫ コラム ≫ 男の珈琲タイム ≫ 千年の里高麗にて
コラム …男の珈琲タイム
高麗の里に行ったのは二十年ぶりだ。
高麗川の清流はなお清く、魚影は細い銀色の光を放っていた。青磁色のカワセミが清流をかすめて翔んだ。菜の花はこぼれるような微笑でハイカー達を迎えいれていた。
眩しいほどの新緑。まさに絶景だ。はるか千五百年も昔、朝鮮半島からの渡来人達は高麗王のもと、百年もの間、この地で栄えたという。当時は、小高い丘の木々はもっと繁く高麗の里を覆い新緑の時は、全ての緑が笑いの絶頂のように萌えていたのだろう。
私の思い出のポケットには高麗がびっしりとつまっている。この思い出だけは断捨離ができず、いまだにポケットを温めている。
高麗王の直系、C君は私の親友だった。英語が得意で、大学・大学院を進み、今では有名私立女子大学の名物教授だ。C君の瞳、というより眼光は透き通るように澄んでいた。高麗王若光の眼、そのままが彼に遺伝したのだろうかと、いまだに忘れることはできない。
A子とはこの清流を眺めつつ、時を忘れて未来を語った。数年のち、別れを告げたのもこの川の畔だった。
重病の父を車に乗せて病院へかけつけたのもこの里の道だった。
何故か、みんな早春から初夏の季節だった。
母を連れて、ジンギスカン料理や手打ちのうどんを食べたのも、この里の料理屋だった。市議会議員に会った。思えば、二十数年も前、この議員を必死になって応援したっけ。
今、うんぞりかえったこの議員をみて、何んといえぬ情けなさを覚えた。「俺は議員しか仕事の場がないんで・・・」この男は歴史の里、高麗におよそ不似合いに見えたが、もしかすると私の勘違いかもしれない。「みんな、こんなものなのだ」と思った方が、妥当なのだろう。帰り、私のファミリー達をよく連れて行った料理屋に寄った。二十年ぶりの私を亭主夫妻は懐かしさにあふれたように迎えてくれた。私は、四十年来の知己、Oさんと昼間から熱燗をほした。八十を越えたOさんは知性あふれる人だ。何のシャレ気もなく服装はキコリのように素朴だ。銀宝という魚は、桜の時季が過ぎるとわずか数ヶ月の生を終えるのだという。Oさんの話が、心にしみて淋しかった。
酔ったせいか、遠い昔の日のファミリーの幻影をみたような気がした。「人生は一酔の夢です」。Oさんの言葉、銀宝のはなし、高麗の里の一日は、すべるように流れ去った。 (鹿島 修太)
バックナンバー
新着ニュース
- さくら草まつり2025(2025年03月22日)
- パールのピアスに憧れて(2025年03月17日)
- 泥酔は人生を変えてしまう(2025年03月31日)
- 二院制はどうなったのか(2025年01月10日)
アクセスランキング
特別企画PR




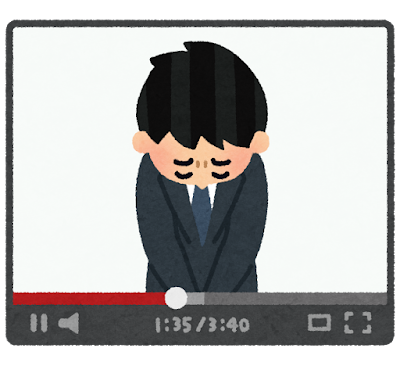


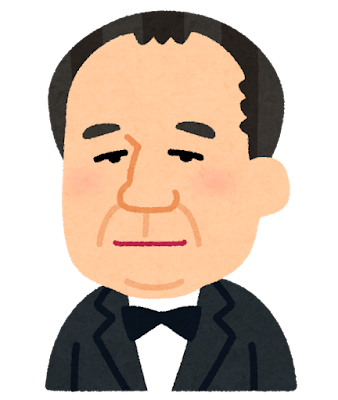








![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](http://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)

