トップページ ≫ コラム ≫ 男の珈琲タイム ≫ 梅雨とカウンター
コラム …男の珈琲タイム
3年ぶりに行った寿司屋は創業50年目だ。
私は久しぶりのカウンターに座って隣りの老紳士の話を聞くともなく、左耳で聞いていた。もとマスコミ関係の仕事でかなり辣腕をふるっていた人らしい。こういう人はきまって地位のある他者を呼び捨てにするのが常だ。そうすることによって自分を少しでも高く見せては人知れぬ快感に浸っているのだ。つまらない人達だ。
私はひとり、今さっき手に入れた池波正太郎の小説を丹念に読み始めていた。凄いと思った。その時代考証の確かさに驚嘆していた。学歴も全くないこの小説家にすっかり魅せられて、寿司さえ忘れていた。
「鹿島さん、ところで何からいきますか?」マスターが半分じれったそうに、さらに付け加えて、訝しげに聞いてきた。
「そうそう、まぐろ、赤身ね」と咄嗟に答えた後、赤身という言葉の対語として白身を思い浮かべた。白身・・・ずっと昔、美津子という透き通るような白い肌の美人と、人生の一時期を過ごしたっけ・・・。私は瞬間とはいえ、あらぬ妄想にかられて独り赤面した。
その時、もう50年も風雪に耐えてきた古い引き戸が、ずるずると鈍い音をたてながら開かれた。見るからに水商売風の美人が店の中の様子をうかがうように顔をのぞかせた。そして、ほっとした身の運びで2席だけ空いていたカウンターの椅子に座った。
「ああ・・・寂しいな、今日が誕生日だというのに私・・・独りなんて」明らかに他を意識してのつぶやきだった。
「ああ、あのね、ええ、君ね、ぼくが君の店に行くよ。ねぇ・・・どうだい?いいだろう?」私の隣の老紳士がその女の顔をうかがった。私はこの艶のない会話を聞き流しながら、再び昔の美津子という名の女を浮かべていた。
とびきり頭が良くて、美貌・・・そしてちょっと私が口にしたことを心に刻んでいて、一生けんめい実行しようとする。それが成せなくとも、また次なることに備えようとしている健気さがなんともたまらなくて、恋心がふくらんでいって、どうしようもなかったっけ・・・。
もう池波正太郎も、赤身も、カツオも頭から消え失せていた。私の人生は四季それぞれが色彩を放ち、この梅雨の夜も心はしっとりと満ちたりて、まさに快晴だ。私は寿司屋の路地を足音高く、まるで勝者の行進のように闊歩した。梅雨だというのに、月は洸々と橙色に照っていた。
さっきのカウンターの女も、昔の美津子も、その夜はみな私の心の中で青みがかった橙色の色彩を放ち続けていた。
(鹿島修太)
バックナンバー
新着ニュース
- さくら草まつり2025(2025年03月22日)
- パールのピアスに憧れて(2025年03月17日)
- 泥酔は人生を変えてしまう(2025年03月31日)
- 二院制はどうなったのか(2025年01月10日)
アクセスランキング
特別企画PR




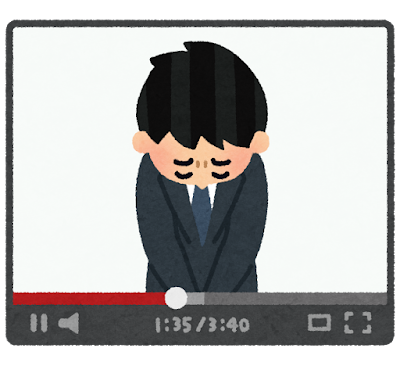


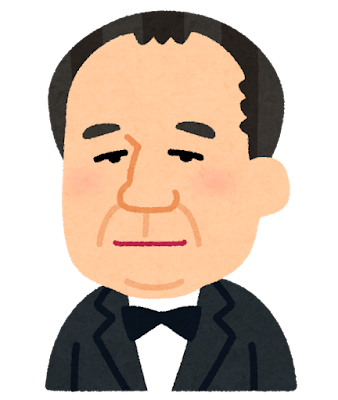








![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](http://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)

