トップページ ≫ 社会 ≫ 佐藤愛子さんのエッセイに頻出する愉快な人
社会
特に埼玉県、さいたま市の政治、経済などはじめ社会全般の出来事を迅速かつ分かりやすく提供。
93歳の作家、佐藤愛子さんの著書が売れている。昨年刊行された『人間の煩悩』(幻冬舎)や『九十歳。何がめでたい』(小学館)は今もベストセラーランキングに顔を出す。前者は過去に書いた作品からセレクトしたもの。2014年刊の小説『晩鐘』の後、断筆宣言をしたはずの彼女が女性週刊誌の執拗な依頼で「半ばヤケクソで書いた」というのが後者。歯切れがよくて痛快な文章は健在だ。
今までの著書は数え切れないほどだが、最近のエッセイ集は『まだ生きている』『これでおしまい』『ああ面白かったと言って死にたい』『かくて老兵は消えてゆく』とか、明日にもこの世からバイバイしそうなタイトルばかり。しかし、中身を読めば、まだまだしぶとく生きていくだろうと思える。体力はともかく、波乱万丈の人生を送ってきた心の強さがあるからだ。
父は大正から昭和にかけて大衆小説で国民的人気を得た佐藤紅緑で、前妻と別れて結ばれた舞台女優との間に彼女は生まれた。詩人サトウハチローをはじめ前妻の子どもたちは不良化し、それぞれが数奇な運命に遭遇する。彼女は両親に可愛がられて育つが、結婚そして敗戦とともに人生が一転する。医者の息子で陸軍の主計将校と結婚するが、夫は腸疾患がもとでモルヒネ中毒になり、治そうとしては挫折する。父・紅緑の死を契機に2人の子供を夫の両親に託して婚家を去り、小説を書き始める。
病院の事務職をしながらの作家修行で、その時の文学仲間と再婚する。彼には親の遺産がかなりあったが、商才がないのに事業に手を出して大失敗、昭和42年の暮れ、2億円の負債を抱える。当時、少女小説や雑文の注文は多かったので、夫の借金返済のために書きまくったものの、焼け石に水だった。そんな壮絶な経験によって「不幸の中にお尻をまくって居座る」覚悟ができたという。この夫とも離婚する。
この話をもとに書いた『戦いすんで日が暮れて』が昭和44年夏に直木賞を受賞する。本人としては出来栄えに満足していない作品であった上に、借金騒動で大変なのにマスコミに追い回されるようになったら身がもたないと心配し、受賞をためらう。「どうしよう?」と相談すると、「しかし、金が入るぞ」と言ってくれたのは前夫と同じく文学仲間で芥川賞候補5回という記録を持つ川上宗薫さんだった。
佐藤さんのエッセイにはいろいろな人々が登場するが、川上さんは最も出番が多いように思える。彼は芥川賞受賞にいたらず、官能小説のほうに方向転換し、情事を描かせたら右に出る者はいないというほどの流行作家になった。それは経験のたまものだったようだ。女性なら誰彼なしに口説きまくる彼を、佐藤さんは時にはあきれながらも愛すべき人物として描く。
私は編集者として、また川上さん考案のピンポン野球の仲間として成城の川上邸にはよく通った。ピンポン野球用の着替えでたまたま応接室に入ったら、和服姿の佐藤さんが来ていて、大きな目でにらまれたことがあった。2人の関係は男女を超えたものだと思っていたが、『まだ生きている』(文春文庫)によれば1度だけ口説かれたという。彼女が「だめよ、宗薫とじゃ近親相姦みたいになるから」と言っても食い下がる。ついに「あたしはそんじゃそこいらの簡単な女とは違うのよ!」とキレると、「そうか……」と引っ込んだそうだ。
この「そうか」がふられ馴れてるというか円熟の一言というか、と佐藤さんは面白がっている。彼女の思い出し笑いが目に浮かぶが、今は亡き宗薫ネタになると文章のトーンまで浮き浮きしているのが楽しい。
山田 洋

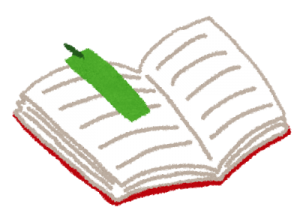



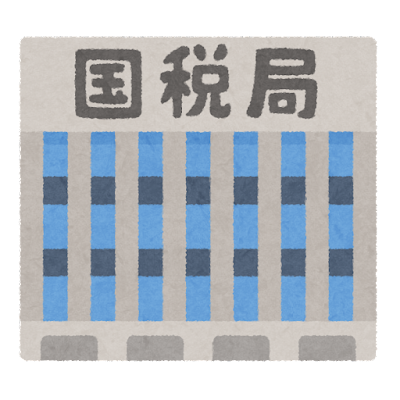


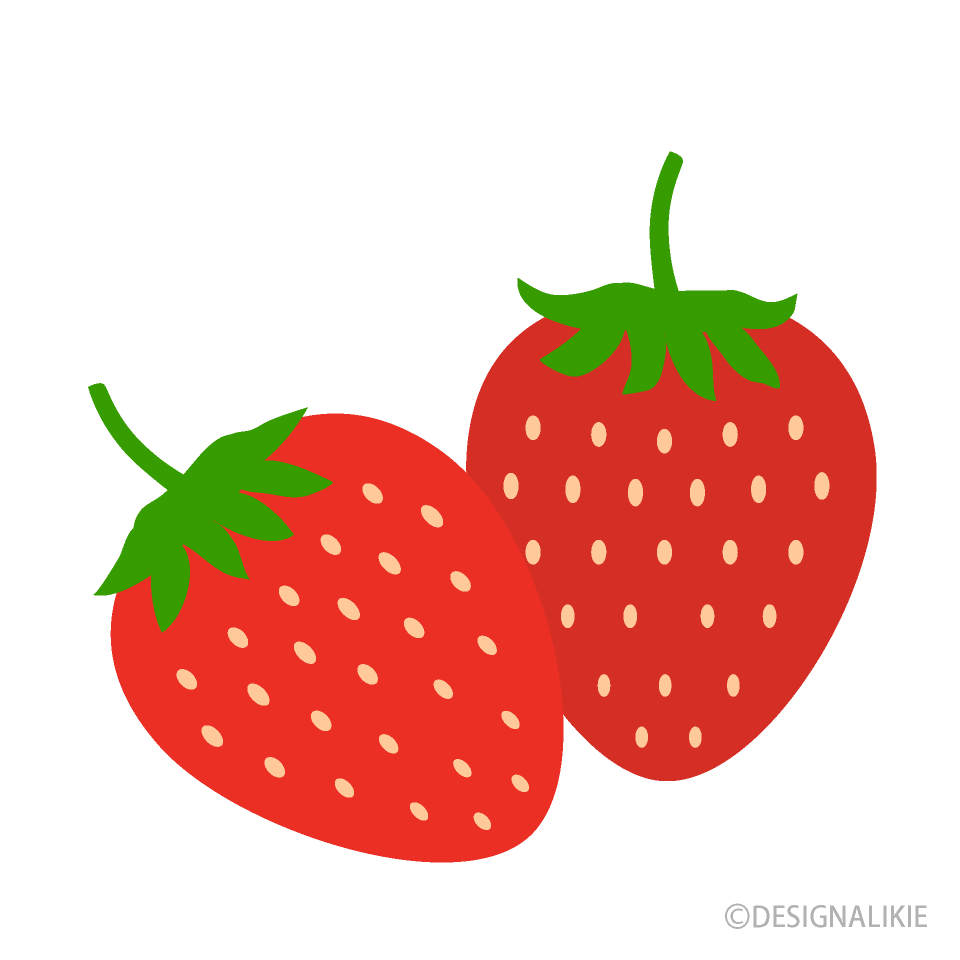


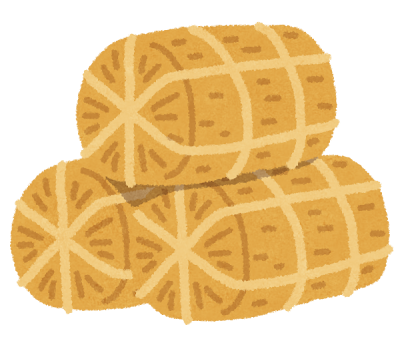





![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](http://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)

