社会
特に埼玉県、さいたま市の政治、経済などはじめ社会全般の出来事を迅速かつ分かりやすく提供。
2月13日に映画監督の鈴木清順さんが93歳で亡くなった。近年は役者としてテレビドラマにも出演していたから、白いあごひげの飄々とした姿を見た人は多いだろう。日本の映画界の興隆と衰退の中で、独自の世界を持ち続けた人だった。
戦後間もない1948年に松竹に入社し、6年後に日活に移籍。56年から監督になり、数々の作品を手掛けるが、彼が社会の注目を集めたのは、67年の『殺しの烙印』が日活社長に「わからない映画」と言われ、翌年に解雇され、上映会へのフィルム貸し出しが禁じられてからだ。映画関係者たちが中心になって「共闘会議」が結成され、裁判闘争にまで発展した。
確かに清順映画では、話に飛躍があったり、シュールな展開になったりするのはよくあることだが、そういう個性まで否定されたらたまらない。評価の高い『けんかえれじい』や『刺青一代』など清順映画で何本も主役を演じた高橋英樹さんは「みんなは『面白いね! 素晴らしいね!』って喝采してるのに、お偉いさんたちはわからないらしいんです。『なんなんだ? あれは』みたいな感じで」と振り返り、このような経営者の姿勢が日活の凋落につながったと悔やむ。
裁判は3年半かかり、和解という形で辛うじて監督側の勝利となったものの、これがもとで10年間も映画作りから遠ざかってしまう。日活での清順監督の待遇はもともとよくなかった。2本立ての映画興行では清順作品はいつも添え物のほうだった。だから当時の看板スター、石原裕次郎さんを一度も使わせてもらえなかった。吉永小百合さんについても同様だ。給料も後輩監督よりも安いくらいだったという。ところが、ある時期から添え物映画の中に独得の手法を盛り込むようになった。監督自身も雑誌のインタビューで「私が撮ろうとしてきたのは終始変わらず娯楽映画であり芸術作品ではなかった」とした上で、「観客をびっくりさせ、あっと言わせるのが映画だと思っているから、仕掛けやサスペンスにこだわってきた」と語っている。
そのような清順映画の中で、私には『刺青一代』(1965年)が印象的だった。途中まで東映の仁侠映画のような展開だったのが、ヤマ場の討ち入りのところでガラッと歌舞伎調の演出に変わる。蓑姿の男が黒子のように突然現われ、男から刀を渡された主人公は、唐傘をパッと広げ、花道を駆け抜けるようにして闇の中に消える。押し入った敵の屋敷の中は極彩色の迷宮のようで、いろいろな仕掛けが次々に飛び出してくる。
1970年代半ば、つまり裁判終了の数年後、映画評論家の上野昂志さんの出版祝賀会に出席したら、清順監督も来ていた。その当時から山羊ひげの仙人のような風貌で、最近の写真で見るのとほとんど同じで不思議に思っていた。今回、この稿執筆のために資料を漁っていたら、「監督は老けたふりをするのが好きだった」という証言があり、納得した。
山田 洋





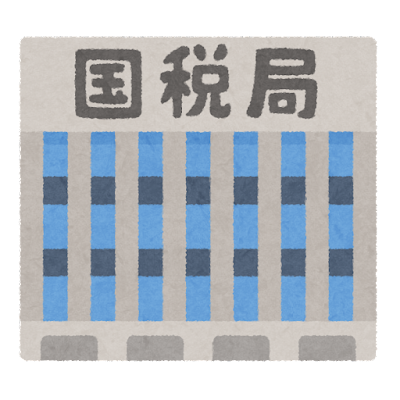


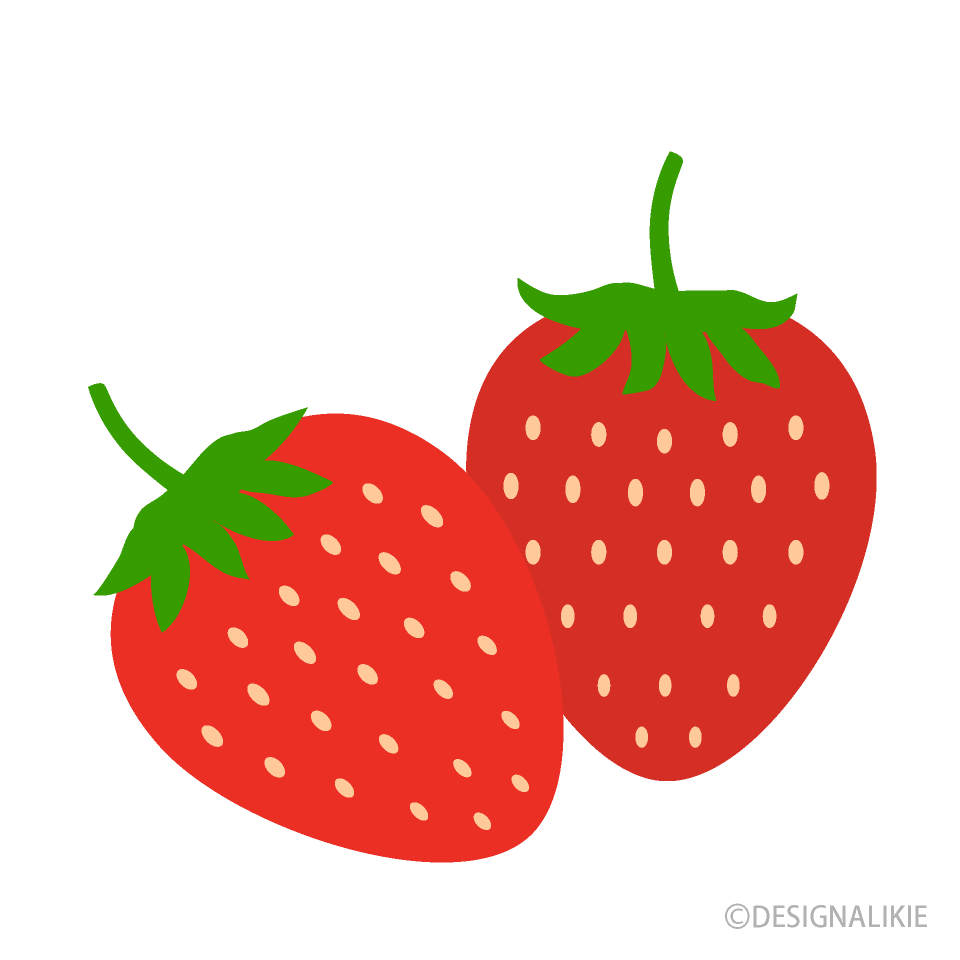


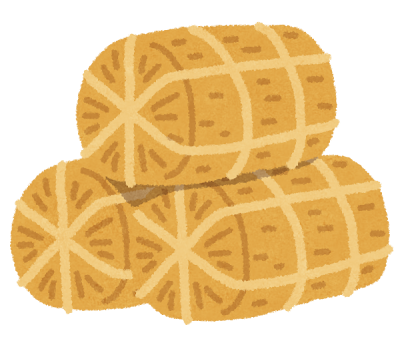





![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](http://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)

