社会
特に埼玉県、さいたま市の政治、経済などはじめ社会全般の出来事を迅速かつ分かりやすく提供。
コロナ禍で中止や延期を余儀なくされたイベントが少しずつ復活している。先日は東京・銀座の博品館劇場で『ぼくたちの音を楽しむ――いずみたくと中村八大の歌物語』という楽しいコンサートがあった。数々のヒットソングを作曲した2人はともに1930年代初頭に生まれ、享年も61~62歳だった。今回はいずみたく没後30年メモリアル企画ということだ。
10年前の2月に私が当欄に初めて寄稿した時にいずみのことに触れた。CMソングをテーマに彼に話してもらうはずが、発売間近の『夜明けのスキャット』の自慢話しかしなかったという内容だった。それでも聞く者を引きつける人だった。
今の暗い世の中で、明るかった昭和の時代に思いを馳せる人たちで会場は埋まった。2人ともすごいヒットメーカーなので、主要曲だけでも限られた時間内で紹介するのが難しいようで、メドレー方式が多用されていた。歌手たちも久し振りの公演で張り切っていた。今陽子
や尾藤イサオら大ベテランも衰えを知らない歌唱力を披露した。
ミュージシャンとしてのスタートは中村八大のほうが早かった。早稲田大学の学生時代からジャズピアニストとして活躍したが、20代の終わりにはジャズブームが去った。その頃、大学時代の知り合いの永六輔に再会。彼の作詞で一晩に10曲を作り、その中の『黒い花びら』が第1回レコード大賞に選ばれた。この幸運の陰には命懸けの苦難があった。ジャズピアニスト時代に麻薬に手を出したのだ。作家・大江健三郎との対談(1962年)で、その恐怖を語っていたが、自力で麻薬断ちをした。それからはジャズだ、クラシックだ、歌謡曲だというカタチを離れて、素直にメロディーを出していこうと思うようになったという。
いずみたくは20代に化粧品会社のトラック運転手をしながら作曲家・芥川也寸志のもとで作曲の勉強をし、うたごえ運動にも参加していた。1957年秋に朝日放送のホームソング・コンクールでグランプリを受賞すると、ラジオやテレビの番組制作の冗談工房に誘われ、芥川の賛意もあり、事務所入りした。だが、給料は運転手時代の6分の1に満たなかった。
ここのマネージャーという濃いサングラスの男がいた。後に人気作家になる野坂昭如だった。放送作家として売り出し中の永六輔もいたし、五木寛之、神吉拓郎ほか多くの才能が集まっていた。野坂と組んでCMソングを量産した。だが、事務所に内緒で引き受けたセクシーなCMソングが世間を騒がせた。これがもとでクビになった2人はCMソングの会社を作った。仕事は目茶苦茶忙しくなったが、物足りなさも感じるようになる。
そんな時、永六輔から「ミュージカルをやろう!」と声が掛かった。これはいずみの夢でもあった。こうして1960年7月に『見上げてごらん、夜の星を』が初日を開け、大成功をおさめた。以後、ミュージカルに傾注していく。野坂も「小説を書きたい」と言ってCMソングから足を洗った。
いずみは文章を書くのが苦手だと言っているが、『ドレミファ交遊録』(1970年 朝日新聞社刊)や『真夜中のコーヒーブレイク』(1974年 講談社刊)を読むと面白いエピソードにあふれていて興味深い。野坂昭如や永六輔との交友は人間臭くて笑いを誘う。長年心血を注いだミュージカルでも、個々の歌手のリサイタルでも厳しい指導に徹した。由紀さおりも佐良直美も今陽子も泣きながらリハーサルを繰り返した。成功すれば、いずみを始め全員が感涙を流したという。
コンサートからの帰路、中村といずみのメロディーが次々によみがえってきた。その中には彼らの作品とは知らなかったものもいくつかあった。(文中敬称略)
山田洋
バックナンバー
新着ニュース
- エルメスの跡地はグッチ(2024年11月20日)
- 第31回さいたま太鼓エキスパート2024(2024年11月03日)
- 秋刀魚苦いかしょっぱいか(2024年11月08日)
- 突然の閉店に驚きの声 スイートバジル(2024年11月19日)
- すぐに遂落した玉木さんの質(2024年11月14日)
特別企画PR

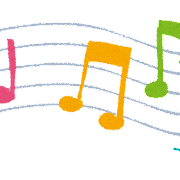




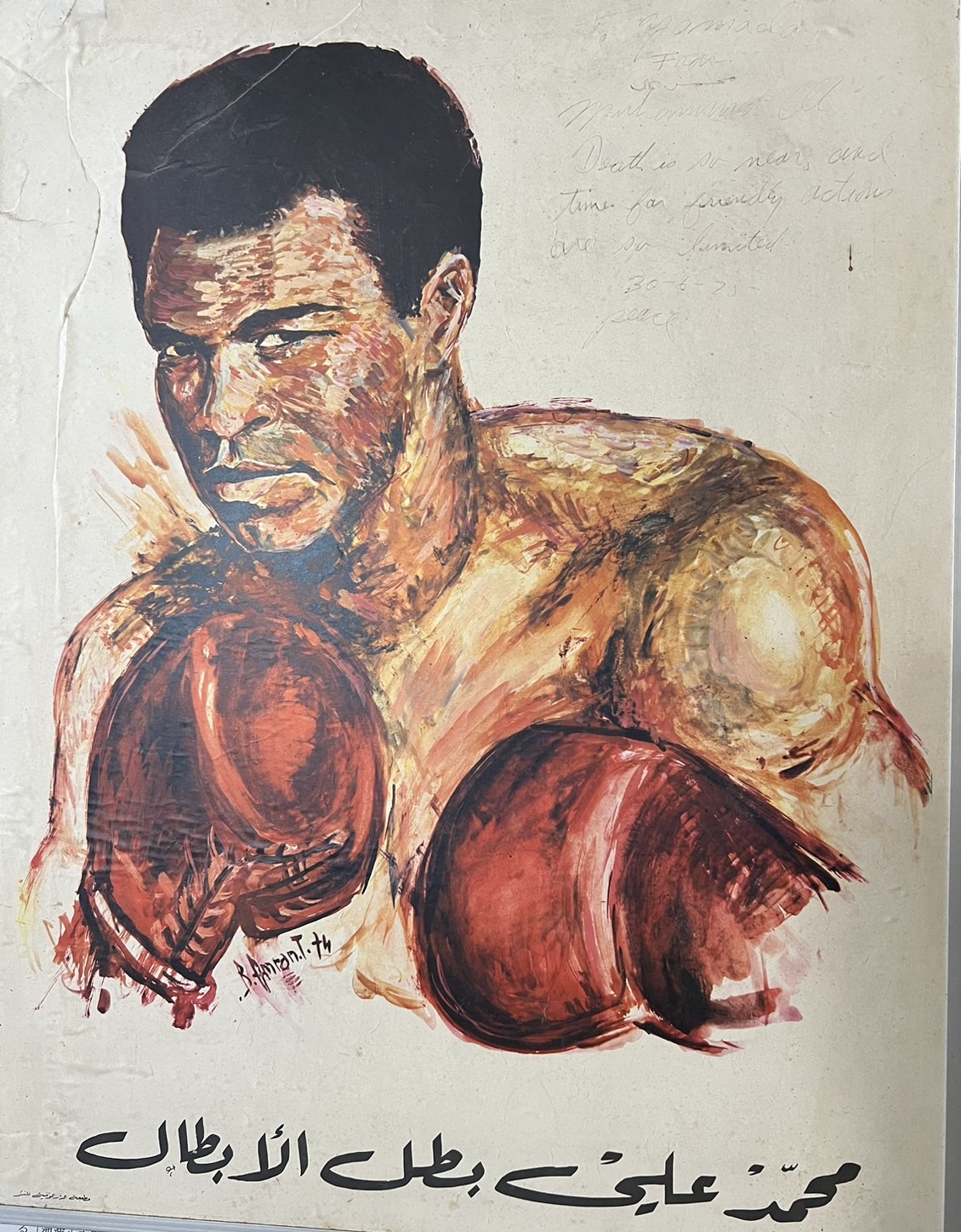










![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](http://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)

