トップページ ≫ 外交評論家 加瀬英明 論集 ≫ 経済・教育など全てで世界の先端にあった
外交評論家 加瀬英明 論集
江戸時代は西洋が生んだ機械こそ欠いていたものの、経済、農業、教育、学問、工芸、余暇活動のどの分野をとっても、世界の先端をいっていた。
それなのにもかかわらず、日本国民のなかに江戸時代というと、封建制度のもとにあった暗い時代だったという先入観に、とらわれている者が多い。
明治初年を指して、開明期と呼ぶことが定着している。開明といえば、文明が開化することを意味している。
今日でも、開明という言葉が用いられているのは、明治以前が暗かったという偏見が、広くいだかれてきたためだ。このような偏見をひろめたもっとも大きな原因といえば、明治政府がつくった。
明治政府は藩長勢力が徳川幕府を打倒して、天下を握ったものだった。新政府は新しい御代を宣伝するために、徳川時代を暗かった時代と否定した。
それに加えてその後、マルクス思想にかぶれた知識人や、学者が封建時代を暗黒の時代として、マルキシズムの型紙に合わせて歴史を乱暴に裁断した。マルキシズム史観が横行したことが、そのような歪んだ見方を強めた。
島崎藤村の小説『夜明け前』という題名は明治が開明期だったということを、前提としている。この作品は幕末の飛騨地方を描いた優れた記録であるが、明治の新時代を“夜明け”だと呼んだのは、その典型的なものだ。
明治初年に、「ザンギリ頭を叩いてみれば、文明開化の音がする。ちょん髷頭を叩いてみれば頑瞑固陋の音がする」と、さかんに歌われた。明治元年に発せられた「五箇条の御誓文」には、「旧来ノ陋習を破リ」と、うたっている。陋習は悪い習慣を意味する。
後藤新平は先の著書のなかで、明治に入ってから江戸の良風と市民秩序が破壊されてしまったことを憂い多。
「王政(明治)維新に際し、嘗て一たび地方人衆の征服する所と為り、精神的には幾ど其蹂躙する所と為りたるより、(略)之が為め一方に旧都市の栄光土泥に委し、都風破れ、自治的旧慣亦多く廃されて地を払ふに庶民し」と述べて、江戸の「栄光」が泥にまみれるようになったと、慨嘆している。
明治以降の日本は西洋化を強いられ、西洋を模倣するうちに、日本の生活文化と精神が蝕まれていった。私たちは西洋化が進むなかで、徳の蓄積を食い潰してきた。
しばらく前に、江戸開府四百年が祝われた。日光東照宮が記念事業として、江戸研究学会を立ちあげた。
私が江戸時代の日本が、世界のなかで庶民がもっとも恵まれていた国だったと書いたりしていたので、会長を引き受けさせられた。
竹内誠館長も理事だったので、江戸東京博物館で講演会を行うなどしたが、このところ休眠状態が続いている。
今日の東京には、江戸の遺産が多く残っている。
いまでも、路地に入ると家の前に花や、植木の鉢が置かれている。わが家も御多分に漏れず、植木を並べている。日本の原風景の一つだ。
私は都心の麹町に住んでいるが、銀座まで三十分ほどかけて歩くと、途中に屑龍が一つもないので、西洋人を当惑させている。
アメリカや、ヨーロッパの都市なら、屑龍が三十メートルおきぐらいに、置かれている。日本では芥を外で捨てずに持ち帰ったし、物を大切に使ったから、芥がほとんどなかった。
幕末の日本を訪れた西洋人は、貧寒な村を通っても、人々が笑みを絶やさず、親切、丁寧で純朴なことに、申し合わせたように感嘆している。道も家のなかも清潔で、身なりがこざっぱりしているのに目を見張った。日本にはヨーロッパや、アメリカだけでなく、世界のどこでも付きものの不潔がみられなかった。
長崎海軍伝習所の教官だった、オランダ士官のカッティングディーケは「支那の不潔さと較べて、日本はどれほど良いか、聖なる国だ」と、書いている。フランス人のボーボワル伯爵も、「不潔、むかつくような悪臭が漂っている、極まりなく下品な支那を離れて、日本は深い喜びだ」と、述べている。
江戸時代は治安がきわめてよかった。江戸は百万都市だったといわれるが、人口が常に百万人を超えていた。
江戸時代の日本の水緑土の景観は、すばらしかった。どこへ行っても、神社や小さな祠があった。人々の崇神の心が篤く、自然を汚すようなことがなかった。
仏教と儒教が七世紀に大陸から伝来して、日本の文化に大きな影響を与えた。土着の信仰である神道と混淆したといわれるが、神道の心のうえに積み重ねられたにすぎなかった。
神道は心と身の回りを、清明に保つことを求める。
江戸は当時の世界とどの都市よりも、飲料水に恵まれていた。
家康が江戸を都市として建設するまでは、伝線病をもたらす蚊やボウフラが湧く湿地が、ひろがっていた。
家康は江戸を本拠地として定めると、良質の飲料水を確保するために、小石川上水と神田上水の造営を命じた。
幕府には神田上水奉行や玉川上水奉行や、玉川上水奉行などの水道奉行が置かれていたが、貴重な水質を守るために、水源に万人が詰める水番屋と水衛所が設けられ、高札が建てられて、洗い物や水浴び、放尿や芥の投棄を、御法度として厳しく取り締まった。
江戸期に編纂された『慶長見聞録』に、「是薬のいづみなれや、五味百味を具足せる色にそみてよし、見にふれてよし、飯をかしひよし、酒茶によし濁水をのぞき去て、清水を万人にあたへ給ふ」と、述べられている。
江戸の人口が増すと、今日の東京都羽村市にあった羽村の取水口から新宿御苑にあった四谷大木戸の水番屋まで、多摩川上流から四十三キロにわたって、石樋、瓦樋、木樋を使って、清水を引き込む地下水路を掘削した。
これは壮大な計画だった。四谷大木戸の水番所から地下水道を通じて、それぞれの町内に設けられた上水井戸まで、届けられた。
日本は物心ともに、ひたすら清明を求める文化だった。今日、東京の水道水が世界一だといわれるのも、日本の精神文化が造りだしたものだ。
およそ、今日の日本文化の形は、江戸時代につくられたといってよい。私たちは江戸時代の恩恵を、大いにこうむっている。
平和が幕藩体制のもとで続くなかで、何ごとについても、、ことさら精神が重んじられるようになった。
武士道という言葉が、江戸時代に生まれた。戦う武術が武道となって、精神面が強調されるようになった。
人々が正座するようになったのも、江戸時代になってからのことだ。それまでは、茶の湯も胡坐をかいて行われた。
女性の幅広い帯から、落語、俳句、歌舞伎、文楽、花火、寿司、天麩羅まで、江戸時代のものである。落語ははじめは軽口ばなしと呼ばれていたが、中期から落し咄と呼ばれていた。
落語は人情噺とも、呼ばれた。江戸期の日本には、人情が微粒子のように、空気のなかに飛んでいた。ちなみに、西洋諸語には人情に当たる言葉がない。同じころのパリや、ロンドン、ベルリンでは、糞尿は住居に面する路上に投棄されていた。そのために、しばしば疫病が発生した。中国や朝鮮も、同じことだった。
ところが、日本では糞尿は商品だった。汲取屋が汲取式便所から糞尿を買って農村まで運び、堆肥として売った。このために、道路が清潔に保たれた。
汚わい屋は立派な職業で、同業組合をつくっていた。
日本は身障者に、やさしい社会だった。
勝海舟の曾祖父は農家の子で、全盲の按摩師だったが、金貸しをして小金を貯め、息子に最下級の武士の株を買った。幕府は身障者保護に手厚く、盲人だけに金貸しを営むことを許していた。
私は盲人福祉に四十年近く携わってきたが、江戸時代は二人の世界的な盲人を生んだ。
杉山和一(一六一〇~一六九四年)は、中国の太く長い鍼を、今日の日本の筒に入った細く短い鍼にかえた、管鍼法をつくった。
和一は今日の和歌山の武家の子だったが、さまざまな苦難を乗り越えて、伍代将軍綱吉の侍医となった。綱吉は和一に求められて、一六八〇年から全国三十ヶ所に、盲人に六年以上教える鍼按摩古所を開設した。
ヨーロッパで最初の盲人学校が、フランスで一七八四年に開校した百四年前に当たる。
もう一人の塙保己一(一七四六~一八二一年)は、今日の埼玉県の農家に生まれ、幼少の時に失明した。人が音読したものを暗記して学び、江戸時代を代表する大学者となった。六百六十六冊にのぼる『群書類従』によって知られるが、保己一が取り組んだ『史料』の編纂は、いまでも東京大学史科編纂所が引き継いでいる。
ヘレン・ケラーが昭和十二年にはじめて来日した時に、東京・渋谷の温故会館にまっ先に駆け付けた。女史はここに置かれた保己一の机を、しばし感慨深げに撫でた。
女史は幼い時から、母親から東洋の日本に保己一という、全盲の大学者がいたことを聞かされて、手本にして努力したのだった。
今日の日本は、物の豊かさが満ちあふれているために、心が貧しくなった。だから、人々が満たされることがない。
私はインドに通った。ガンジーは倫理を重んじて、自ら糸車で糸を紡いで、人々が質素な生活を送るべきことを説いた。
ガンジーは道徳と、節制を説いたアジアの最後の指導者となった。
その後のアジアは、鄧小平や、シンガポールのリ・クワンユーが代表したように、経済成長を最重要な課題とするようになった。
経済が倫理から切り離されて、欲望の経済となった。
徳の国富論 資源小国 日本の力 第五章 美意識が生き方の規範をつくった
バックナンバー
新着ニュース
- さくら草まつり2025(2025年03月22日)
- パールのピアスに憧れて(2025年03月17日)
- 引っ越し費用が100万円(2025年03月10日)
- 二院制はどうなったのか(2025年01月10日)
特別企画PR

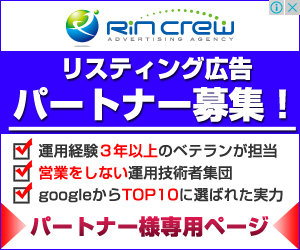

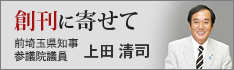
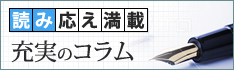

![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](http://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)

