トップページ ≫ 社会 ≫ いま日本は滅びつつある(第1回) -母なる日本の胎内に戻って出直そう-
社会
特に埼玉県、さいたま市の政治、経済などはじめ社会全般の出来事を迅速かつ分かりやすく提供。
かつての日本と日本人は、国としても民族としても質が高かった。
外交評論家 加瀬 英明
日本人であれ、外国人であれ、明治が偉大な時代だったことを否定する者はいまい。
明治の日本を創ったのが、江戸時代の日本の教育だった。輝かしい日本を築いたのが、藩校であり、全国津々浦浦に二万軒以上もあった庶民の教育機関だった寺子屋だった。寺子屋では往来物という教科書が使われ、今日七千種類以上がのこっているが、すばらしいものだった。
といって、あの時代の日本に余計な節介を焼く文科省が存在しなかったから、教育がまともだったとはいうまい。
あの時代の日本と日本人は、国家としても民族としても質が高かった。
教育のありかたは、その国の姿を映す鏡である。家庭と学校-小学校、中学校は、社会の縮図だ。家庭と学校がどうなっているかということによって、その国の健康の度合を計ることができる。
今の日本では青年による秋葉原における無差別殺人事件をはじめとして、兇兇(まがまが)しい事件が相次いでいる。社会を構成している基本単位である家庭が崩壊したことを、慨嘆させられる。家庭と学校はそのときどきの国の精神を現わしており、表裏一体のものとなっている。
国民が経済繁栄がもたらした享楽に溺れるうちに、児童にとってもっとも重要な場である家庭と、教育が取返しがつかないまで虫食まれている。そして教育に携わる者が児童の自主性とか個性を伸ばすことや、人権や平等を祭壇に祀って拝跪するうちに、教育が荒廃してしまった。
自主性や人権や、差別や格差をなくすことが徳目であるかのように錯覚しているが、このような目標は徳目となりえない。これらの理念は徳目と遠くかけ離れているのに、影響力を持つ知識人や教育を司る人々が、いつのまにか徳目として摩り変えてしまった。小学教育で平等を重んじるあまり、全員が駆けっこで手を繋いで走って、同時にゴールに入るといった滑稽なことが真面目に行われた。
平等といえば、ロシア革命が成就したころのロシアの作家のエフジェニー・ザムヤチンが頭に浮かぶ。ジョージ・オーウェルの研究者であれば、ザムヤチンの『われら』(1920年)と、ボルシェビキ政権のもとの農村を舞台にしたパロディの『同志チュリーギンの熱弁』(26年)が、『一九八四年』と『動物農園』の下敷きとなったことを知っている。
ザムヤチンの『フィタの最後の物語』(1922年)は、フィタ村の善意に溢れた村長が村民の幸せを願って、村民に平等を強いる話である。禿げた村民に合わせるために、男女の村民全員に髪を剃ることを命じる。村に精神薄弱者が一人いるために、全員にその真似をするように強いる。
ザムヤチンの作品は1950年代末にニューヨークで学んだ時に、英文学の講座でオーウェルを理解するために読むように勧められた。ザムヤチンは1931年にソ連から脱出して、その年にパリで客死した。
ザムヤチンと同じ時代のロシアの作家のなかにユリ・オレシャがいて、『羨望』(1927年)という短篇がある。この作品を教えてくれたのも、やはりニューヨーク時代の知人だった。日本で訳書がでているから、なじみがある読者もいよう。
『羨望』の舞台はやはりボルシュビキ政権初期の農村である。反動思想の持ち主の青年によって語られる。バビチェフという共同農場(コムーナ)の食堂を仕切る共産党員が理想のソーセージをつくろうとして、的外れなことばかりするが、すべてを擲(なげう)って献身的に働くのを目のあたりにして、羨望する話である。
この作品はいったい諷刺なのか、作者の真情を語っているものか、よく分からない。理想のソーセージは新しい社会を象徴しているが、そんなものが存在するはずがない。
日本で教職を志す人々が邪しまな心をいだいて教壇に立っていると思いたくないが、善意に駆られているにせよ、理想の-というよりも、粗悪なソーセージづくりに没頭するうちに、教育を台無しにしてしまった。小人が正義感にとり憑かれて熱中すると、災いを招くことを教えている。
この八月にアレキサンドル・ソルジェニーツィンが逝った。ソルジェニーツィンは『収容所群島』(1973年)のなかで、社会主義時代が第二の農奴の時代だったことを明らかにしている。無慈悲な収容所の所長が旧体制の地主と入れ替っただけで、収容所の住人たちは体力をすり減らすだけの賦役を強いられ、かつての農奴とまったく変わらなかった。
私はニコライ王朝末期のロシアをニコライ・アレクセーエビッチ・ネクラーソフ(1921年~78年)の詩を通じて、体験することができた。六本木の住人で、その界隈にいくつか小さなビルを経営していた大原恒一氏が、日本におけるネクラーソフ研究の第一人者だった。大原氏と浅酌するうちに、ロシア文学について手解きしてもらった。ネクラーソフは民衆詩人として知られているが、農奴や引き船人夫など、ロシア国民の多数を占めた下層民の悲惨な生活に憤った。
大原氏はしばらく前に他界したが、モスクワ大学文学部を卒業していた。その著書『赤鼻のマローズ』(論創社、平成6年)のなかで、帝制のもとの農民は「死ぬことのほうが生きるより楽」だったが、革命後も変わらなかったと断じている。
今日では、社会主義運動は権力亡者たちによって利用されただけだったことが証されている。ソ連の崩壊とともに社会主義のイデオロギーは、歴史の芥箱(ごみばこ)に放り込まれてしまった。
もとより人は協調する動物ではない。天性によって競争する。社会主義政権内部の凄惨な権力争いが、人の性を証している。社会主義はボタンを大きく掛け違えていた。
だが、日本は物が余るほどまで溢れて、幅広い自由が許容されているのにもかかわらず、享楽に酔って家族と社会を束ねてきた徳目が疎かにされているために、社会が瓦解しつつある。
ソルジェニーツィンは『収容所群島』を西側で出版したために、国外へ追放された。強制収容所で八年を過ごしていた。『収容所群島』が西側で高い評価を博すると、圧制と闘う知識人の象徴となった。政権はデタントを戦術としていたから、ソルジェニーツィンを収容所へ戻すわけにゆかなかった。
ソルジェニーツィンは1974年に西側へ亡命した。英雄として迎えられたが、良心に忠実な求道者であったから、西側社会のありかたに組しなかった。西側の俗悪・不道徳な消費文化を糾弾した。日本も同じような惨状に陥っている。
自由で豊かな日本も、芥箱のなかに投げ込まれたようにみえる。
私たちは先人から受け継ぐべきであった、素晴しい資産である生活文化を壊してしまった。いつのまにか人として生きる教えがすたれ、そうするうちに自らの手によって仏教でいう末法の世を招き寄せた。社会主義も自由市場主義も薔薇色の社会をつくるはずだったのに、破綻をもたらした。(つづく)
バックナンバー
新着ニュース
- さくら草まつり2025(2025年03月22日)
- パールのピアスに憧れて(2025年03月17日)
- 泥酔は人生を変えてしまう(2025年03月31日)
- 二院制はどうなったのか(2025年01月10日)
アクセスランキング
特別企画PR




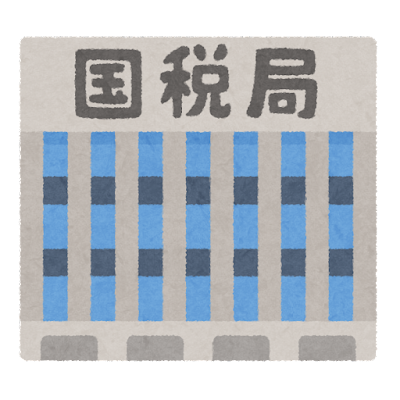


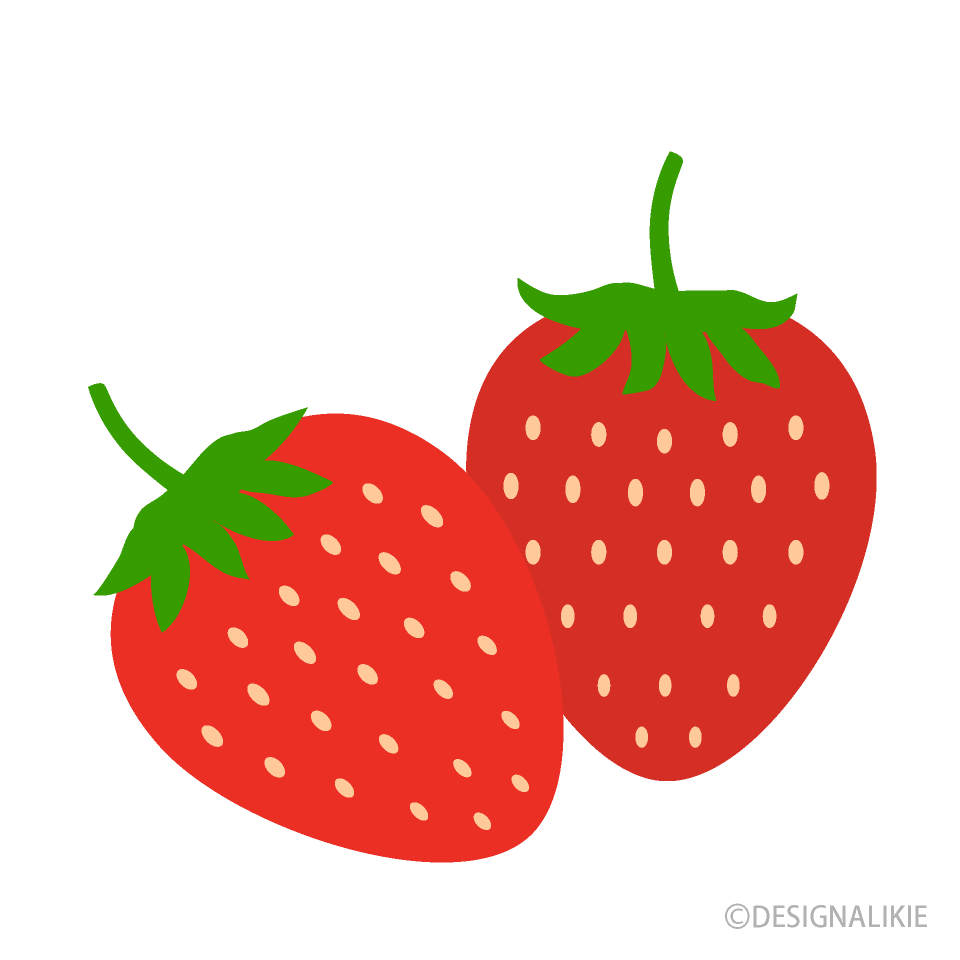


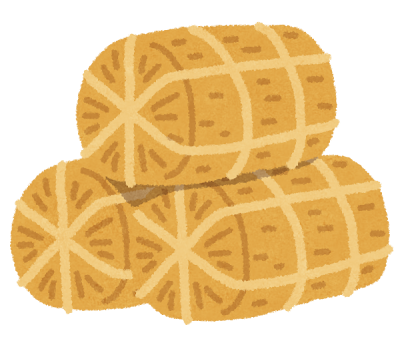





![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](http://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)

