社会
特に埼玉県、さいたま市の政治、経済などはじめ社会全般の出来事を迅速かつ分かりやすく提供。
戦後の青春スター第1号とも言われた女優、三條美紀が亡くなった。近年まで映画やテレビで脇役として活躍していたから、スター時代はともかく、彼女を画面で見た人は多いだろう。彼女は1948年、19歳の時に出演した「山猫令嬢」で人気を獲得したが、この映画こそ、戦後間もない頃に大ヒットした大映の母もの映画の第1作なのだ。
三益愛子が母親役のこのシリーズは、大映で1958年までに31本も製作され、途中の1955年に他社製作の2本があるから、合わせると33本になる。今でこそ、渥美清の「男はつらいよ」シリーズの計48本が世界最長の映画シリーズとしてギネスブックにも認定されているが、それには26年もかかっており、10年で30数本というのは驚異的と言える。
「男はつらいよ」では監督と主要な配役は固定されているが、母ものシリーズは主役の三益以外は流動的だ。「山猫令嬢」の成功もあり、第2作「母」、第3作「母紅梅」など計6本に出演した三條美紀は、シリーズに最も起用された1人だ。
夫を亡くしたり離別したりして戦中戦後を苦労して生きてきた母と子(たいていは女子)の物語で、子供の幸せのために自己犠牲の道を選ぶ母に日本中の女性が感情移入し、涙を流した。「私は学がないけど、お前だけは……」というような台詞が頻出する。母と子が別れ別れとか反目する設定が多いが、最後はハッピーエンドが用意されていた。
私も子供の時に母と一緒に1本か2本見た憶えがある。数年前にスカパーの日本映画専門チャンネルで大映の全31作品が放映された際にも何本か見た。午前中の放送だったので、三益の切々たる演技で朝からウェットな気分にさせられるのは閉口したが、私と同世代の白鳥みづえや松島トモ子が子役として好演しているのが印象的だった。
大映の母もの映画の成功を見て、他社も同種の作品を出したが、うまくはいかなかった。三益の母ものでないと客を呼べなかったのだ。
興業的には大成功した大映の母もの映画も、批評家たちには酷評された。「お涙ちょうだい」で話も古臭く、新しい時代に生きる姿勢が欠落していると指摘された。これについては、当時、三益と内縁関係にあり、大映の専務取締役になった作家、川口松太郎が母もの映画に深く関与したことに起因しているようだ。「日本映画は生きている 第5巻 監督と俳優の美学」(岩波書店 2010年刊)の中で愛知県立大学の野沢公子教授は、川口を「1939年の空前のヒット作『愛染かつら』の原作者として大衆の感情に訴えるノウハウを熟知し、新生新派を統括する経営能力を見込まれた」として、「日本社会の激しい変化を視野に入れつつ、手馴れた『お涙もの』と『母もの』をメロドラマの図式にした」と分析している。実際、川口は大映の31作品中、原作、原案、脚本で計11本にかかわっていた。
三益自身は女優として母もの映画に満足してはいなかったようだ。抑えめの表現ながら、映画への不満を口にしていた。彼女が評価されるのは、大映を退社して舞台に復帰し、1959年から翌年にかけて371回のロングランとなった「がめつい奴」(菊田一夫・作)においてだ。主役のお鹿婆さんの演技で初めて賞(芸術祭賞とテアトロン賞)を受けた。
川口とも正式に結婚し、4人の子供に恵まれた。ところが、1973年から川口家には子供たちの不祥事が続発し、「子育てに失敗した日本の母」などと週刊誌に書き立てられた。三益は1982年に71歳で膵臓癌で亡くなった。
三條美紀の訃報から母もの映画を思い出したのが母の日だったのも何かの縁かもしれない。
(山田 洋)






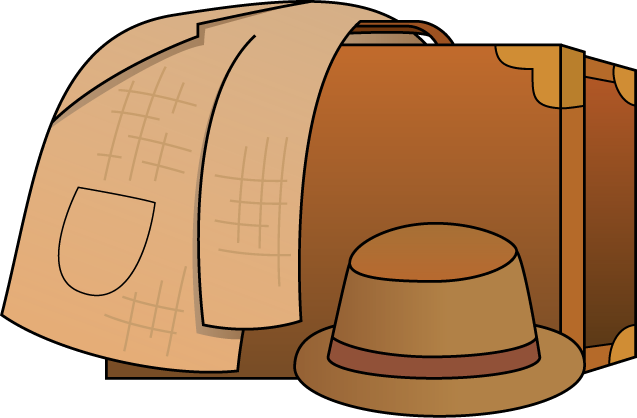
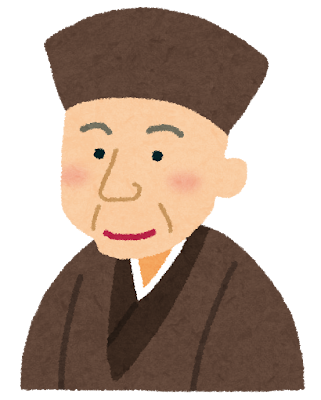

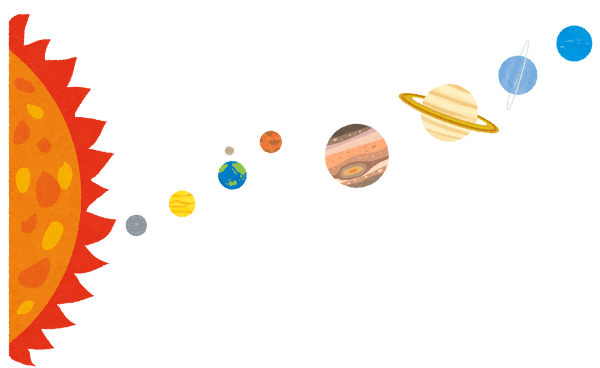






![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](https://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)

